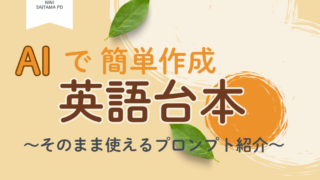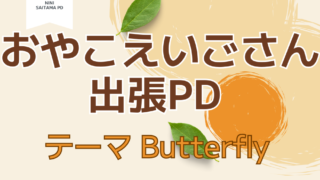こんにちは Niniです👩🍳
日々の授業準備おつかれさまです
自分でまとめた記事をもとに実践した授業の取り組みを報告する記事です。
授業を計画する際の参考になったら嬉しいです。
以前まとめた記事と一緒にぜひご活用ください。

授業のふり返り
◯使用教科書
啓林館 わくわく理科 3「3.チョウを育てよう」
◯ 今回使用した授業案
なし
言い訳:運動会で教材研究や相談の間がなかったから
◯ 授業の感想
初めての教室飼育。子どもたちのキラキラした瞳に教師のやりがいを感じ、本物からしか得られないものに気づかされた。
グループ観察が有効だった。
◯ 授業の反省
生き物を育てることは大変。授業の時期になると餌となるアブラナ科の葉が取れなくなる。
差異点や共通点からふしぎを見つける過程がなかった。
以下、詳しくふり返ります
授業前に
モンシロチョウの卵 発見!
近くの空き地にアブラナが茂る場所があり、モンシロチョウが飛び回っていたためよく見たところ卵を発見!今まで忙しさにかまけてモンシロチョウの飼育は避けてきた身でしたが、娘にとっても面白いだろうと飼育に挑戦しました。
用意したもの
- プラスチック卵パック(孵化〜小さい幼虫用)
- ミニトマトなどのプラスチックパック(大きくなった幼虫用)
- ティッシュ
- 卵つきのアブラナを茎ごと
- 霧吹き
- マスキングテープ(採取日の記録用)
- ピンセット
- ハサミ
卵の孵化を調整する
こちらを参考にたまごの孵化を調整しました。
チョウを育てよう ふ化直前の卵を配って,観察中に・・・・3年 たまご,ふ化の観察
初めは恐々冷蔵庫に卵を入れましたが、孵化をコントロールしても問題なく全ての卵が孵化し、成虫になりました。
葉についた卵は、卵パックで管理しました。上部に空気穴を開けて、濡らしたティッシュを敷き、各部屋にセットします。葉が乾燥するため毎朝霧吹きをしました。
卵パックの便利さをあげると、
- 持ち運びが楽。
- 場所を取らない。
- 透明で中が見える。
- 観察しやすいように葉を切り分けて保管できる。
卵から2齢期(青虫の姿がわかるようになった頃)くらいまではこれでいけます。
餌の用意
モンシロチョウの幼虫といえば、キャベツの葉を思い浮かべる方も多いと思いますがこれだとけっこう難しいと感じました。
そもそも身近にキャベツ畑がない。また学校でキャベツを育てることもありますが、虫の食害でモンシロチョウにあげるほどの葉を確保することが困難です。
よって私は教科書には出てこなくてわかりにくいけど、アブラナの葉を用意しました。
アブラナは葉ごとに柔らかさが違うため、小さい幼虫には上の方の柔らかい葉を。たくさん食べる大きい幼虫には下の方の葉をあげました。この時、ハモグリバエの卵が産み付けられている葉は誰も食べてくれないため避けておきます。
根元に水で濡らしたティッシュを巻きつけておくと葉が長持ちしますが、気を抜くとカビが発生するため要注意です。
授業案は使用せず、ただひたすら観察

おすすめの授業から何も選ばず、ただひたすら観察をしました。
なぜならは、授業の展開を選ぶ余裕が自分になかったから……。この時期は運動会の練習が半日ぶっ通しであったり、急な授業変更があったりして毎日いろんなものの調整続き、夕方はその日のトラブル報告をして即帰宅。てんてこ舞いな日々でした。
やってみた感想は小グループ(3~4人)で観察すると特徴に気づきやすくなり、絵の描き方や言語化が上達しました。
より詳しく、単元の導入・実験1・実験2・終末に分けて報告します。
単元の導入・卵の観察
この授業を行うにあたって準備したものは、以下の二つ。
- 虫眼鏡
- モンシロチョウの卵10個
- 飼育セット
「春の生き物を探した時にチョウが飛んでいたね。」というところから、チョウを見つけた場所や様子から「何をしていたのだろう?」という問いました。
すると、葉や花を食べていた。いや、花の蜜を飲んでいた。2羽でケンカ・縄張り争い。卵を産んでいた。などいろいろ。
そこで卵のお披露目。
子どもたちはその小ささから見つけることに時間がかかるも、見つかると大きさや形、色に注目して観察を始めました。
幼虫の観察
幼虫の観察は生まれたばかりと大きくなったものの2回しました。隣の班と大きさを比べたり、食べている様子やフンをした様子など嬉々として観察していました。
大きくなると脱走も考えられるため、各班に一つトマトパックに入れた幼虫を蓋をして渡していました。
この大きい幼虫はあと数日でサナギになるべく、よく食べ・よく動くため脱走対策にキッチンの排水溝用のネットをパックへかけていました。
サナギの観察
モンシロチョウのサナギはトゲトゲした形が特徴的です。これをなんとか描き表そうと四苦八苦していました。写真では細部に目を凝らす必要がないため、これぞ観察の醍醐味だと感じました。
よく見ると体を支えるための?1本太い糸が見えます。これを発見した子はこの日のスーパースターになりました。
成虫の観察
羽化はだいたい16時前後だったため、子どもたちは立ち会うことができませんでした。家で羽化した様子の動画を観せると歓声が上がりました。前もって以下のサイトを確認し、羽化も遅らせることができれば良かったと反省。
3 チョウを育てよう P.7 【参考1】冷蔵庫を使った羽化時間の調整
その後、放蝶は昇降口から行いました。皆で「チョウ バイバーイ」と大きな声でお別れです。子どもたちは飛んでいってしまうことが惜しい様子でした。
単元のまとめ
完全変態の様子や順序を動画を観ながら確認しました。羽化の様子が見れず残念がっていたため、羽化の動画はいくつか観せました。
ふしぎがいっぱい (3年)アオムシのへんしん(2) NHK for school
アゲハのそだち方 NHK for school
サナギの下にオレンジ色の液体が垂れていた様子を「チョウがうんちした!」と報告してくれた子が、動画を観て羽を広げるために使った体液だったことがわかり嬉しそうでした。
実物を見て気付いたからこそ、動画で学ぶことができるなぁとしみじみ思いました。
テスト
購入している業者のテストを実施。
これといって良くもなく、悪くもない結果でした。しいていえば、「成虫」と回答できない子が数名、モンシロチョウ、チョウと答えていたため、単元ごとに出てくる身近ではない理科の用語?は都度丁寧に確認する必要があると思いました。
全体の振り返り

「3.チョウを育てよう」を振り返ってみると、以下の2点でしょうか。
- 実物に勝るものなし
- グループ観察で観察力アップ
動画で見たらチョウの変態は一瞬でわかるし、1人で観察すれば早いし静かで楽だけど、わざわざ飼育して、わざわざグループにすることで得られるものは何倍もあって、これらを選択していく価値に気づきました。
この単元をきっかけに「学校だから・人がたくさんいるからこそできることってなんだろう。」と考えて学習活動を計画しています。
おわりに
虫が好きな子が大活躍する単元!その子にはぜひ「昆虫博士」の称号を言い渡してあげてくださいね。
苦手な子も見ていくうちに愛着が湧く子もいれば、最後まで拒否の子もいます。好みや考え方は「みんな違ってみんないい」けど、命は尊いものであることを忘れずに指導したいものです。
皆さんの教材研究・準備の一助になれたら幸いです。

Have a nice day!