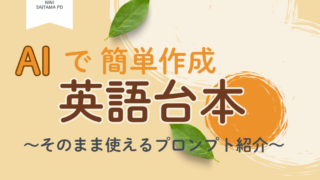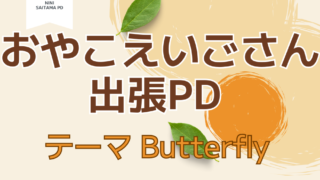こんにちは Niniです👩🍳
日々の授業準備おつかれさまです
自分でまとめた記事をもとに実践した授業の取り組みを報告する記事です。
授業を計画する際の参考になったら嬉しいです。
以前まとめた記事と一緒にぜひご活用ください。

授業のふり返り
◯使用教科書
啓林館 わくわく理科 3「風とゴムの力のはたらき」
◯ 今回使用した授業案
【やるキット NHK for school 「動き方がかわる?」】
◯ 授業の感想
「予想の手がかり」という考え方が難しい。
かざぐるまの実験は手軽かつ風の強弱に目を向けやすくてよい。
◯ 授業の反省
暑さも考慮した活動場所の用意が必要
予想の立て方の指導が足りなかった
以下、詳しくふり返ります
授業前に
実験キット
今年度キットを購入しました。
選んだキットはこちら↓

キット選びの際に話題に上がったことは、以下の2点についてでした。
- プロペラの有無
- タイヤのつくり
それぞれ詳しく紹介します。
プロペラの有無について
今年は学年の意向でプロペラ付きを購入しました。
ものつくりが好きな子が多いため採用しました。
授業の中で取り上げることはできませんでしたが、単元の最後に走らせることができました。
「どうして動いたのだろう?」など問い、グループで考察し、さらなる実験を計画したら楽しいだろうなぁとは思いますが時間の都合上、夢のまた夢です。
タイヤのつくり
2社のキットを比較して、数十円安い方を手に取り「安い方でいいですよねぇ。」と言いかけたところでタイヤが違うことに気づきました。
A社のタイヤはプラスチックが薄く、まるでスナック菓子のスピンのよう!(安くて美味しいですよね)
かわって採用した「はくぶん」のタイヤは厚く、表面の凹凸もしっかりしていました。

皆さんも車系のキットは、主にタイヤに注目して選んでみてください。
送風機のチェック
送風機はコンセントタイプのため、場所が限定されてしまいました。
手動の送風機は、場所を気にせず使えて便利です!
理科主任さん!
古い送風機を使っていましたら、手動の買い替えをおすすめします!
実験場所
この実験が始まる数日前から熱中症指数が厳重警戒を連日叩き出し、体育館使用中止に。
冷房がある視聴覚室は体育の授業で使用不可。
「どこで車を走らせろと??」
まさかのまさか。教室と廊下でした。
狭いし、人は通るし、グループ活動なんてあってないようなもの。
皆さんの学校はどうされているのでしょうか…。
この暑さを把握して、場所の確保は事前にしておくべきと肝に銘じました。
「動き方がかわる?」やるキット NHK for school
おすすめの授業から選んだ授業案は、
「動き方がかわる?」やるキット NHK for schoolです。
選んだ理由は、根拠のある予想を立てる手立てが豊富で良いと思ったからです。
やってみた感想は、1年生の生活科で作っていたかざぐるまが登場したため既習内容をもとに風の力について考えることができました。
しかし、「予想の手がかり」という意味が伝わらず、予想を立てる際に「なぜなら〜」と経験や動画で観たことを根拠としてあげることが非常に難しかったです。
より詳しく、単元の導入・実験1・実験2・終末に分けて報告します。
単元の導入
この授業を行うにあたって準備したものは、以下の二つ。
- かざぐるま
- 思考ツール「キャンディチャート」
かざぐるまの作り方は、工程が少ないわくわくさんの動画を参考にしました。
思考ツール「キャンディチェーン」のワークシートは、やるキットを参考に作成。
キャンディチェーンの「もし〜なら」、「どうなる?」まではどの子も書けました。
しかし、「なぜなら〜」の枠は一向に書ける様子がなく何度も噛み砕いて説明してやっと数人書けました。
本来、1時間で終わる内容が2時間扱いになってしまいました。
改善策
「なぜなら〜」を考える時は「予想の手がかり」の写真を提示する。
グループで話し合う。
「なぜなら〜」を書くことへの執着を解いて言葉を削ぎ落とす。
実験1 風のはたらき
教室にて机を四隅に寄せて6班編成の2交代制で実施。
送風機の風が他の班の車に当たっていたり、背後の車に気づかずぶつかったり、
はちゃめちゃな時間でしたがとりあえず終了。
「風は強いと物を動かすはたらきが大きくなる」
だいたい理解はできたようです。
実験2 ゴムのはたらき
「次はゴムのはたらきで車を走らせよう!」と導入は特になく、そのまま始めました。
実験に入る前に重点的に指導したことが「手応え」です。
ゴムを引き伸ばした時の戻ろうとする力を「手応え」といいます。
「手応え」「手応え」「手応え」「手応え」
と声に出して覚えました。
4年生の「空気と水の性質」でピストンを押した時の様子を表現する際にまた「手応え」が出てきます。馴染みのない言葉は理解しにくいため、ゴムを伸び縮みさせながら押さえました。
ゴムの方が伸ばす長さによって明らかに走る距離が変わりますし、車が走る速度も速いため盛り上がりました。
時間と場所の都合上、5cm,10cmはグループで、15cmは教師が廊下で走らせました。
「ゴムは伸ばすとものを動かすはたらきが大きくなる」
こちらもだいたい理解はできたようです。
終末の応用・発展的な時間
奇跡的に気温が低く、体育館で活動。
走らせる車の種類ごとに棲み分けをしました。
- 伸ばすゴムの長さを変える
- ゴムを二重にしたり、大きいゴムを使う
- プロペラ
- 送風機2台
- 荷物運び
- 競争やリレー
30分間、ただひたすら子どもたちは車を組み立て、走らせ、遊び尽くしていました。
子ども同士が声を掛け合って教えたり、比較したり自然と学び合う姿が見られて学級の成長を感じました。
遊びから学んでいくことを再確認しました。
今後はもっと遊ぶ時間を設定して、自分たちで気づき考え挑戦する機会を設けたいです。
テスト
購入している業者のテストを実施。
たくさん車を触り、走らせたおかげか成績良好!
問題文の読み取りに時間がかかる子も自分から率先して実験に取り組んでいたため、車の動く様子をよく理解していました。
自分ごととして学習に向かうためには教師のは控え目が良いと反省です。
全体の振り返り
「風とゴムのはたらき」を振り返ってみると、以下の3点でしょうか。
- 子どもは遊びから学ぶ
- 広くて涼しい場所の確保
- 「予想の手がかり」は慣れるまで待て
根拠のある予想は、4年生の理科が主に指導する学年です。
急がずじっくり子どもたちが学び、4年生で花開くように仕込んでいきます。
おわりに
3年生理科で初めての物理学。
自分たちで作って、走らせて、とっても楽しい単元だなぁとつくづく思いました。
この楽しさは他の教科ではなかなか味わえないワクワクですよね。
次回の単元は「昆虫」です。夏休み中に教材研究をして虫嫌いの子も興味を持てくれたら嬉しいなぁと構想中です。
皆さんの教材研究・準備の一助になれたら幸いです。

Have a nice day!